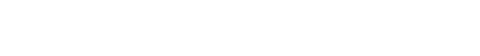展覧会・イベント 第24回 ふるさと学習講座 終了
テーマ 「宮腰御蔵と大坂廻米」
江戸時代の宮腰にあった宮腰御蔵の役割の一端を紹介します。
御蔵とは、藩主の直轄領の年貢米が収められる蔵で、加賀・能登・越中の各地に
70か所置かれていました。
宮腰御蔵は、能登・越中からの年貢米が廻送されて、金沢に運ばれて消費されたり、
大坂へ船で廻米されて売却され、加賀藩の財政を支える重要な役割を果たしました。
今回は御蔵の機能から宮腰町の重要性を考えます。
【開催日】 令和5年9月9日(土) 13時半~15時
【場所】 銭屋五兵衛記念館内
【講師】 上田長生先生 金沢大学人間社会研究域
国際学系(国際学類・人文学類)准教授博士(文学)
【参加費】 無料
【定員】 50名 事前にお申し込み下さい
※石川県民大学の受講対象講座となってります。
ふるさと学習講座終了しました。
参加者の多くは金石にお住まいで、メモを取りながら熱心に聞いていらっしゃいました。